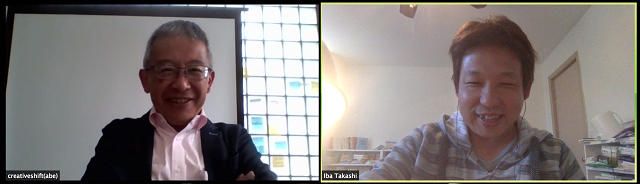2019年2月に出版された『クリエイティブ・ラーニング:創造社会の学びと教育』(慶應義塾大学出版会)は、200ページにおよぶ序章と、教育界で活躍する4名の専門家との対談で構成されています。今回は、本書籍の編著者である慶應義塾大学総合政策学部教授・井庭崇氏と、対談相手の一人である探研移動小学校主宰・市川力氏へインタビューを実施しました。
「クリエイティブ・ラーニング」(創造的な学び)とは何なのか、クリエイティブ・ラーニングに何を期待しているのか、また、クリエイティブ・ラーニングの実践の核となる「ジェネレーター」という担い手について、話を聞きました。クリエイティブ・ラーニングについては前編にて、ジェネレーターについては後編にてご紹介します。
本書をすでに読まれた方はもちろん、まだ読んでいなくてもご理解いただける内容です。ぜひ、未来の教育を考えるきっかけとしてみてください。
クリエイティブ・ラーニングがふたりの学びの共通項
——本書の構想にいたるまでのバックグランドを教えてください。
井庭:僕はこれまで20年近く大学で教えながら、「教える」ということを実践的に探究してきました。同時に、複雑系の研究として、「複雑なことを複雑なままどう理解するか(どう学ぶか)」について考えてきました。つまり、「教える」と「学ぶ」を考え続けてきたわけです。一方で、10代のころは「映像作家になりたい」と思っていて、映像をつくる、ものをつくるということにずっと関心があり、そういう「創造」の実践もしてきました。結果として、「学び」と「創造」が結びつき、今回の本につながりました。
市川:僕は、大学では学習心理学、発達心理学などを専門とし、人が学んで知識を身につけていくとはどういうことか、ということが関心の根底にありました。20代から40代にかけて13年間、アメリカで、在米駐在員子女の日本語学習と帰国準備をサポートする塾を運営していました。90年代のアメリカでは、プロジェクト型の学びが盛んに実践されており、私も、生徒たちの宿題のサポートを通じて、プロジェクト型の学びに触れたわけです。その後、帰国して「東京コミュニティスクール」の創設に参画し、初代校長に就任。ここで、プロジェクト型の学びを中心にした探究する学びを実践していたところ、井庭さんとの出会いがありました。2017年からは、探研移動小学校を主宰し、学校外での学びの可能性を試しています。
——本書での対談を通じて、お二人の思考が化学反応を起こして、新しい何かが生まれるというようなことはありましたか?
井庭:はい、とても。僕たちが会うと毎回必ずそうなるので、いつものことなんですけれども(笑)。市川さんとの会話は、単なる情報交換ではなく、創造的対話という感じで、いつも刺激的です。そして常に、その場で新しい何かが生まれます。
市川:10年ほど前、井庭さんと最初に会ったときに、「二人それぞれ違う立場でつくる学びをしてきたけれど、共通するところがあるよね」と意気投合。それで、「お互いにやっていることを分析してみよう」と二週間後に再度会ったのです。そうしたら話が盛り上がってしまって、結局、研究室で10時間以上もしゃべっていましたね。そのときに生まれたアイデアが、半年後には論文になって、アメリカ・ポートランドの学会で一緒に発表しました。最初の出会いからそんな感じでしたね。
井庭:実は市川さんとは、7年ぐらい前から「一緒に本を書こう」という話をしていました。実際に原稿を持ち寄って会うのですが、その度ごとに話が盛り上がって、新しいことが生まれて、結局まとまらない(笑)。それで、とりあえずお互いまた宿題として持ち帰るのですが、二人とも考えと実践の進化のスピードが速いから、次に会ったときは、また新しい捉え方や発想が増えていて、まとまりようがない(笑)。この本の対談も、2014年に二人が語って盛り上がったことを、それぞれ持ち帰って探究し実践して、2016年に再び対談したものをベースに、さらに大幅に加筆・修正してまとめたものを掲載しています。
市川:そういう意味で、今回は、対談本の可能性を知りましたね。僕たち書き手がどうアイデアをジェネレイトしているか、そのプロセスがみえるのがこの本の面白さです。文章を推敲していると、どんどん内容をアップデートしたくなって、それをまた井庭さんがアップデートして。
井庭:そうそう、対談原稿をお互いに往復書簡のような形で加筆・修正し、進化させながら完成させたのがこの本の対談パートなんです。対談しながらその場でまず生まれ、その対談原稿に手を入れているときもまた新たなものが生まれ、そういうものも含めて、現時点での重要で面白い話になるように編み上げ、この本の中に込めました。そういうふうにつくられた読み物としても面白いものになっていると思います。
——お二人のスピード感とか高揚感も伝わってきそうですね。
井庭:そうそう。僕と市川さんの対談は、よく「二人で盛り上がっていて、すごく楽しそうなのだけれど、スピード・展開が速くて置いていかれる。何が起こっているのかわからないという、ちょっと悔しくもあり刺激的だ」と言われることがあります。生(なま)の対談は、その場ですべて理解に至らなくても、「なんだ、それ?何やら面白そうだな」と思ってもらうことが好奇心につながるので、僕はそれでよいと思っています。対談本なら、自分のスピードで読んでもらえるので、また違ったよさがありますよね。専門外の人にもわかりやすいように補足したり、注釈を入れたりしているので、僕たちの「ジェットコースター対談」(笑)を生で聴く前の準備・導入書としてもおすすめです。
200ページの序章は、冒険のはじまり
——本書は、序章だけで200ページもあることも特徴的ですね。
井庭:そうなんです。わかりやすくしっかりと書き込んでいったら、結果として、そんなに長くなってしまいました。僕自身これほどのボリュームになるとは、予想していませんでした(笑)。編集者に最初は「ここに20ページぐらいの序章が入ります」と伝えていたのですが、書き始めると、いつのまにか200ページに!序章だけで1冊の本として出版するという方法もありましたが、後半の対談を含めて全体として有機的につながっているので、僕としては、このセットで丸ごと世の中に出したかったわけです。そこを編集者も理解してくれて、非常にありがたかったです。
——序章では、どのようなことを伝えたかったのでしょうか。
井庭:ピアジェ、ヴィゴツキー、デューイ、パパートなど、学習・発達に関する重要な研究者の考えを取り上げ、実際に彼らの言葉を引きながら、「構成主義」という学びの思想・理論を紹介しています。この序章を書くために、書籍を100冊以上取り寄せ、半年かけて読み込みました。もっと簡単に「構成主義とはこういう考え方です」と短くまとめてしまうこともできたのですが、それよりも、本人たちの言葉にたくさん触れてもらい、感じて味わってほしいと思い、そこにこだわってまとめまいた。引用元の文献もたどれるようになっていますので、入門的な資料としても使っていただけます。
市川:言葉遊びで表現すると、この本は「序章(じょしょう)が助走(じょそう)になっている」といえますね。序章を読んでいると、「これから森に入って行くぞ」という冒険前のワクワク感があります。そして、後半の冒険=対談に入っていくと、「そうか、こういうことだったのか」と解き明かされる。その後、さらに「なにかやりたい」、「これをやってみたらどうだろう」とモヤモヤ感が残るというか、とにかく行動したくなるのです。
井庭:まさに、読者からは、「序章が解説となり、対談で実践を学べる」、「序章の復習として、対談を読める」という感想をいただいています。実は、本のつくり方としては、後半の対談部分の編集が先で、その部分を入稿したあとに、対談で出てくる重要なキーワードをしっかりと解説するために、後から序章を執筆・編集しています。
実践者の視点で、難しいことをわかりやすく
——最終的に、序章・対談を合わせ672ページの厚みになり、存在感のある本となりました。
井庭:刷り上がってきた厚い本を見て、僕自身があまりの厚みに「え?」と驚きました(笑)。とはいえ、前半の序章から後半の対談まで、すべてが有機的につながっているので、やはり丸ごと1冊の本とすることに意味があったと思います。新しい概念(本書のテーマの「クリエイティブ・ラーニング」)を訴えるにあたっては、骨太なものをつくって世の中に提示していきたいと思いがあったので、嬉しいですね。
でも、いろいろうれしい感想や書評をいただいてはいるのですが、思っていたほどには感想・書評が上がって来ていないなとも感じています。おそらく、あの厚さの影響は大きいのではないかと思います。厚い本というのはそういうことがあるのかと、出してみて、初めて気がつきました。薄い本なら、読者も短時間で読みやすいし、その感想を書くのもしやすいでしょう。でも、あそこまで分厚いと、読むのにも時間がかかり、内容も多様でたくさん含まれているので、感想も書きにくいんだろうなぁ、と。その意味では、「失敗したなぁ」と(笑)。
だから、みなさんにお願いしたいのは、あの本は全部読み終わってから1冊丸ごとの感想を書こうとするととても大変なので、章ごととか、話題ごととか、部分的に感想を書いてもらえるとよいのではないかと思います。そして、何度かに分けて書いて、そのあとから、それらをとりまとめるようなまとめの感想を書いていただくのがよいと思うのです。みなさんの感想は、著者としては、とても刺激的なので、みなさんが感じたことや考えたことを読みたいと思っています。ですので、ぜひ部分的に、気軽にこまめに書いてください!(笑)
市川:僕の周りでは、600ページというヘビーな本であっても、「このヘビーさが良かったよね」という声が多いですよ。多くのことが詰まっているので、発見を繰り返しながら、大事に読んでいる人が多いのではないでしょうか。これを読むこと自体が、クリエイティブ・ラーニングの歩みですね。家に置いて、何かあったときに立ち帰れる辞書的、入門書的な使い方もできますし、ずっと読まれる本になると思っています。
井庭:「躊躇していたけれど、読み始めたらスラスラ読めた」、「楽しく読めた」という感想が多いのですが、この本が難しくならなかった理由はおそらく3つあります。
まずは、特に序章の話ですが、ピアジェなどの言葉を引用するとき、同じ人の言葉の中から一番わかりやすい表現を選んで拾ってくることで、難しい表現を徹底的に排除しました。
次に、僕が普段取り組んでいるパターン・ランゲージをつくる作業、つまり、「本質的で難しいことを、わかりやすい表現に置き換える」という経験・得意を活かすことができました。そのため、本書で扱っている構成主義の考え方について、本質をつかんでもらいやすくなっているのではないかと思います。
最後に、これは本書全体にいえることですが、実践者の目で書かれているということです。僕は、思想史や教育学の専門家ではありませんので、ピアジェやヴィゴツキーを取り上げるときも、そういう学術的文脈ではなく、実践の文脈で取り上げています。対談も、みなさん、学びや教育の実践的な研究者です。ですから、引用する言葉も、「実践者として、どう活かせるか」という観点で選んでいます。だからこそ、教育の現場にいる方から見ると、「刺激になる」、「面白い」と感じていただけるのではないでしょうか。
市川:補足しますと、クリエイティブ・ラーニングとは、わからないからこそ挑戦して、つくってみて、さらにわからないことが見えて…というように、「どこまで行ってもわからないことを追い続ける」ということです。考えることは辛いことなので、なるべくなら考えずにラクしたいのですが、クリエイティブ・ラーニングではそれは許されないわけです。つまり、わからないことに対して、前向きにつきあいながら、何かつくっていくのがクリエイティブ・ラーニングです。
この本は、わからないことを読みやすく書いてあるので、読者は、わからない自分を楽しめるのです。わからないことを友達にするというか、わからないことを掲げながら生きるということを直球で語っています。
読者は、わからないことに挑戦する自分を見るために、あるいは、わからないことをずっと追い続けるために、この本を側に置いておきたくなるのです。わからないまま放置しておいてもいいし、何度も「こうかもしれない」、「ああかもしれない」と読み返すことで、発見ができる本だと感じています。
——難しいけれど読みやすい本…。どのような読者層を想定しているのでしょうか。
井庭:教育に関わる人はもちろん、親、地域の人、企業で働く人…すべての方に読んでいただきたいですね。「学び」「成長」というのは、人が生きていく上で誰でもが関係することですし、学びにつながる経験をつくるということは、学校だけの問題ではなく、多くの人に関係することだからです。この本は、幅広い読者層を想定して、個々の分野の専門的表現には注釈をつけるなど、だれでもが読み込んでいただけるものになっています。クリエイティブ・ラーニングの考え方や方法をどう自分の仕事・組織に活かすのか、あるいは、子どもたちがクリエイティブ・ラーニングを実現するために自分に何ができるのかについて、それぞれが考えることができると思います。
なぜ、クリエイティブ・ラーニングなのか
——今回の著書では、クリエイティブ・ラーニングの可能性と重要性について訴えています。未来を見据えた時に、今の日本の教育ではいけないという危機感を抱いているということでしょうか。
井庭:そうですね。問題解決や新しい発想で物事に取り組んでいくために、また創造的に生きていくために、もっともっと創造的な経験を積んで、創造実践の力を養っていくことのできる教育に変わっていかなければならないと考えています。そういうことの重要性をすでに感じている先生方も現場には少なからずいます。でも、そういう先生方も、学校という場・制度がもつ制約のなかで板挟みになり、動きが取れなくなっているのが現場です。一部の人が動くというだけではなく、もっと大きく全体として変わっていかないといけないのです。そのために、世の中の多様な層に向けて、何が大切かをきちんと訴え、そのビジョンを共有していくことが大切だと思い、本書をつくりました。
本書の対談では、異なる分野の実践的な研究者(あるいは、探究する実践者)のみなさんをお招きして、それぞれの観点からこれからの学びについて語り合いました。こうすることで、これからの学び、特にクリエイティブ・ラーニング(創造的な学び)について多面的に考えることが可能になっています。そして、多くの方に関心をもっていただけるものになったと思っています。自分が一番興味のあるテーマの章から読んでいただくのでよいのです。
——クリエイティブ・ラーニング=創造することで学ぶ、とは具体的にどういうことでしょうか。
井庭:典型は、何かを「つくる」ことで学ぶということです。あるいは「つくる」なかで学ぶ。例えば、何かの芸術作品をつくるというのも創造的な学びとなりますし、研究・探究の活動というのも創造的な学びです。
勉強と研究って、多くの人にとっては、同じようなものだと見えるかもしれませんが、そうではありません。未知なる現象の捉え方をつくったり、分析結果をつくったりするのが研究です。研究はとても創造的なのです。
「大学院に進む」というと、よく「勉強が好きなんだぁ」と言われたりしますが、勉強と研究は全然違うものです。しかも、僕は創造しながら学ぶクリエイター・タイプの研究者で、勉強が好きなのではなく、面白いし楽しいから、本を読むし、話を聞くし、考えるわけです。つまり、僕がしているのは勉強ではなく、探究であり、創造的な学びなのです。
僕が20代のときに研究していた“複雑系”科学では、複雑な対象は分解するとその本質が失われてしまうので、どうしたらその本質を失わずに理解できるのかが考えられ、「構成的理解」というアプローチがとられました。複雑なメカニズムをコンピュータ上で実現し、その複雑なものを観察することでその本質を理解するのです。解析的な学問ではなく、つくって理解するという構成的な学問です。これは僕が今やっているパターン・ランゲージをつくるということにも通じています。

——パターン・ランゲージをつくること自体も、まさに創造的な学びということなのですよね。
井庭:そうです。たとえば、『旅のことば:認知症とともによりよく生きるためのヒント』(丸善出版)をつくったときも、僕自身は認知症のことは知らないままつくり始めました。つくる過程で本質が見えてきて、はじめて「認知症とともに生きるとは、こういうことだ」と理解するのです。つまり、わかったからつくるのではなく、つくるプロセスのなかで、わかっていくのです。
本書の序章でも、小説家の村上春樹さんや映画監督の宮崎駿さんの言葉を引用していますが、彼らも、それぞれの言葉で、「つくる中でわかってくるものがあり、そのためにつくっているのだ」という意味合いのことを言っています。そこに僕はものすごく共感しましたね。パターン・ランゲージをつくることに限らずとも、読者のみなさんも、文章を書くことで思考が整理されて分かっていくという経験をされたことがあるのではないでしょうか。それは、創造的な学びなのです。
日本でのクリエイティブ・ラーニングの難しさ
——市川さんは、13年間アメリカで教育に携わってこられました。井庭さんも、現在アメリカでお子さんを公立校に通わせていらっしゃいます。アメリカと日本の教育の比較の中でクリエイティブ・ラーニングについて感じることはありますか?
市川:アメリカでは、公立校でも地域ごとにユニークな取り組みを行うことが可能です。たとえば、最先端の学びが成立する条件が、少人数クラスであれば、行政やコミュニティ、保護者主導でその条件に合わせて学校を変えていく、そういう柔軟性があることが、アメリカの教育現場の特徴です。その代わり、クリエイティブ・ラーニングに関しても、進んでいる地域とそうでない地域と、かなりの格差があることを実感しました。
日本でも、制約が多い中で、どうやって子どもの好奇心を刺激して、面白い学びをしていくかということを、研究している先生は少なくありません。実践面のノウハウは、日本は決して引けをとりません。ただ、そういう先生が全国に点在していて、線としてつながらないので、いつまでたっても広がらないというのが日本の現状です。
井庭:いま娘が通っているアメリカの公立の小学校では、「STEAM」(Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics)が掲げられて、授業とイベントに取り入れられているだけでなく、保護者向けの集まりでも、「SEL」(Social Emotional Learning)という言葉なども普通に飛び交っていて、衝撃を受けました。日本でも私立の学校ならばそういうこともあるかもしれませんが、地域の公立の小学校でもそういう新しい考え方が浸透し、取り入れられているのです。日本の教育現場の問題点として感じることは、新しい方向に変えていこうという意欲と発想を持っている教員が一部いる一方で、学校全体としてはこれまでの体制・仕組みからなかなか変わって行きにくいということがあるのではないでしょうか。
——今の日本の教育現場で、クリエイティブ・ラーニングを実現するために、できることは何でしょうか。
市川:学校内での学びだけにこだわらないことでしょうか。日本ではアメリカのようにどんどん学校を変えたり、つくったりという仕掛けがしにくいと感じています。では、「本当に学校でないとできないのか。学校外ですればいいのではないか」という問題提起が、僕が主宰する「探研移動小学校」のベースにあります。僕は子どもたちに「先生」ではなく「おっちゃん」と呼ばれているのですが、おっちゃんと子どもたち数人がいれば、一緒に何かをつくる学びの場は、すぐにできるのです。実際に、そういう取り組みをしたい大人はいっぱいいます。つくる学びの場を実現するために、自分の本業を捨てる必要はありません。たとえば、学校の先生が、週末は学校外でつくる学びをしてもいいですし、ビジネスマンが、週末に学びの場をつくってもいい。それによって、何か新しいアイデアが湧いたりして、本業にもいい影響があったりします。
また、母親も「常に自分が子育てをしないといけない」と考える必要はなく、僕のようにつくる学びをやっている「おっちゃん」や「おばちゃん」に預けてもいいわけです。もちろん自分で子どもたちと一緒に、つくる学びをしてもいいですね。
パターン・ランゲージは、クリエイティブ・ラーニングをサポートするツール
井庭:市川さんは、あえて学校外に軸をおいていますが、僕は学校だろうが、学校外であろうが、クリエイティブ・ラーニングを実践したい人を支援したいと思っています。まさにそのツールになるのが、「パターン・ランゲージ」なのです。
10年以上、様々なテーマでパターン・ランゲージを作ってきて、相当数のパターンが蓄積されました。でも、テーマごとの提供だと、そのテーマに興味がある人しか手に取ってくれません。本書では、様々なテーマのパターン・ランゲージのなかから、教育、学び、そしてクリエイティブ・ラーニングをサポートするツールになるものの概要を、すべて掲載しました。正直、「ここまで出してしまっていいのか」という迷いもありましたが、あえてここまで出したのは、「クリエイティブ・ラーニングをサポートするパターンが、こんなにあるのか」ということから、「じゃあ、やってみようか」と背中を押すことができるかもしれないと思ったからです。パターン・ランゲージというツールがあることで、いろいろな人がクリエイティブ・ラーニングを実践できるということを伝えたいし、応援したいと思っています。
クリエイティブ・ラーニングの担い手としての「ジェネレーター」
——本書では、クリエイティブ・ラーニングにまつわるキーワードがいくつも出てきます。そのひとつである「ジェネレーター」は、お二人の対話から生まれたそうですね。
市川:クリエイティブ・ラーニングの新たな担い手として、「ティーチャーでもファシリテーターでもない人が必要だよね」と。そういう対話の中から、「generator=ジェネレーター」という概念が生まれました。簡単にいうと、学び手と一緒に学びを生みだしていく、つくり出していくという人を表しています。
井庭:最初は、「generative participants(生成的参加者)」と表現していたのですが、長くて言いづらいし、もう少し言いやすく覚えやすい言葉にしようということで「ジェネレーター」 になりました。
本書では、書名の「クリエイティブ・ラーニング」も含めて、これからの社会のキーワードとなる言葉がたくさん出てきていて、「ジェネレーター」もそのひとつです。読者の感想を聞いていると、今のところは「クリエイティブ・ラーニング」よりも、「創造社会」とか「ジェネレーター」というキーワードの方が響いているようで、面白いですね。よいと思います。
市川:「ティーチャー」、「ファシリテーター」、「ジェネレーター」はそれぞれ違い、どれが良いとか悪いではありません。ただ、これからの創造社会においては、従来の「ティーチャー」「ファシリテーター」に加えて、「ジェネレーター」という役割が必要なことは間違いないのです。「ティーチャー」や「ファシリテーター」にはテクニックが必要で、それを身につけないとなれない気がしますよね。ところが「ジェネレーター」に必要なのは好奇心だけです。人間は根源的に好奇心を持っていて、自分にはないと感じるならば、ただ、大人になって忘れてしまったか、封印しているだけです。好奇心を解き放つことを体感すれば、だれでもが「ジェネレーターになれる」と実感できるのです。

「クリエイティブ・ラーニング」の先にある社会とは!?
——家庭や学校、企業などで、「クリエイティブ・ラーニング」を実践していくと、個人、そして30年後の社会はどう変わっていくのでしょうか。
市川: 僕は、30年後の未来は、みんなが、健康で幸せで生きている世の中であってほしいなと思っています。ところが、今の日本社会には、「将来はAIが人間の仕事を奪う」など、不安をあおり、先行きが暗いという空気感が漂っています。確かに、これからは「誰かがラクをさせてくれる」、「誰かに守られる」という状況を、井庭さんのいう「消費社会」のやり方で、お金を稼いで買うというやり方で維持するのは難しいでしょう。でも、これからの「創造社会」においては、物質としてのモノも、幸せや新しい意味といった抽象的なコトも、自分でつくっていく必要があります。「つくるというのは、モノだけではありませんよ」というのは、本書の中で井庭さんも論じていますよね。さらに、今までは、新しい意味をつくれるのは、スティーブ・ジョブズのような一部のスーパースターだけでしたが、「だれでもつくることができますよ」というのが、これからの「創造社会」なのです。
井庭:本書の序章「デューイの『経験の連続性』と『経験の再構成』」にも書いていますが、いま現在の経験は、これからの未来の経験をつくるための礎となります。小さなものでも、何かをつくった経験がなければ、大きなものはつくれません。最初は、家庭や学校での小さな経験でもかまいません。「つくる経験」を重ねていくことで、問題が起きたときに、どう解決できるかを考えられる人がもっともっと増えてくると思います。
今までの日本の教育で行われてきたことは、どちらかというと、「覚える経験」、「定まった正解がある問題を解く経験」が多かったと思います。これからは、学校の中でも外でも、社会の随所で、モノをつくったり、自分たちなりの答えをつくったりという経験がなされ、つくる経験値を上げてきた人たちが出会い、プロジェクトを組んで共働し、社会に大きな影響を与える。あるいは、世の中をつくっていく。そういう連鎖が起きると思っています。
市川:僕が学校外の活動に重きを置いているのは、決して学校に関心がないからではありません。ただ、僕は、「学びは学校でしなければいけない」とか、「学校外の学びとは?」、「家庭での学びとは?」と、学びの場を分けて考える必要はないと思っています。学びというのは、自分たちの身の回りで普通に起こっていることですから。だから、「自分たちでできることがあるよ」と伝えたいのです。僕があえて、「だれでもジェネレーターになれますよ」と言っているのも、そういうことです。日々の小さな営みに意味を見出しながら、自らをジェネレートして、自分の生活をつくりあげることを、それぞれが楽しめるような社会になるのではないか。それによって、自分の生き方が変わったとか、楽しくなったという人が少しずつ増えるのではないか。そして、そういう人が集まって、社会が構成されたら幸せなのではないかと思っています。その意味でも、このタイミングで『クリエイティブ・ラーニング』が世に出たことには、大きな意味があると思っています。
<前編・完>
(取材・執筆 鯰美紀)
『クリエイティブ・ラーニング:創造社会の学びと教育』(井庭 崇(編著), 鈴木 寛, 岩瀬 直樹, 今井 むつみ, 市川 力, 慶應義塾大学出版会, 2019年2月出版)